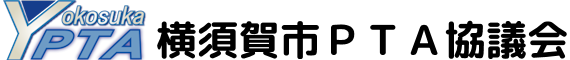目次
Chapter1 なぜ今、規約を見直す必要があるのか
Chapter2 規約チェックポイント、マストの4項目
Chapter3 規約改正ToDo
~Chapter1 なぜ今、規約を見直す必要があるのか~
規約、目を通したことはありますか?
PTAはボランティアだから、そんな堅苦しい事言わなくても。
規約とかそういうのはよくわからないので。
自分の代では改定とかやりたくないなぁ。
改定したいけど、どうすればいいのか全く分かりません。 こんなふうに考えている方も多いと思います。
でも、規約は結構大事なんです。PTAは任意団体ですので、規約が間違っているからといって法律違反になるようなことはまずありません。しかし、うっかり見過ごすと訴えられるような大きなトラブルになることがあります。
たとえば、
「加入した覚えがないのに、学校に提供した教材費の引き落とし口座から、PTA会費が引き落とされている。違法なのでは?」
こんな事で訴訟になってしまったケースがあります。
(2023年7月教員によるPTA会費返還請求=鹿児島裁判)
裁判にならなくても調停で全額返金することになったケースは多々あります。規約に「加入届をもってPTA会員となる」であったり、会費の徴収方法や学校との業務委託契約書(準委任契約)についてきちんと書いてあれば、それに従って加入届もとっていたでしょうし、こんなトラブルにはならなかったはずです。
ここでは、トラブルに発展しやすい規約のチェックポイントを提示しますので、お手元の規約をチェックしてみましょう。
~Chapter2 規約チェックポイント、マストの4項目~
①規約チェックポイント、マストの4項目その1.
加入は任意、退会も任意
※令和5年国会で当時の岸田首相と永岡文部科学大臣が「入退会については保護者の自由である」と答弁。
もし「強制加入」であるような記載があれば、トラブルになった場合に言い訳できず、逃げ場を失います。加入の要件が書かれていないと、もし「加入した覚えがないのに勝手にPTA会費が引き落とされた」という訴えがあった場合に、「加入していたはず」という反論の根拠を失い、不利になるでしょう。
チェックする規約の個所はここ↓
【第●章 会員】
☑「●●小学校に入学すると●●小学校PTA、▲▲市PTA協議会、■■県及び日本PTA全国協議会の会員となる」のように意思にかかわらず会員になるようになっている。「入会希望者は、入会届を提出する」のように入会に手続きが必要であることが書かれていない。(自動入会)
☑「この会の会員は本校に在籍する児童の保護者および本校職員とする」のように自由意思にかかわらず会員になるように書かれている。「この会へは、自由意思で入会し、また退会できる」のように任意で入会するように書かれていない。(強制加入)
☑そもそも加入について書かれていない。(会員が加入している根拠がない)
☑入会について「任意」「自由」の記載はあるが退会について記載がない。(退会について記載がないと任意加入とは言えない)
記載例)下記の3項目は記載マストです。
第●章 会員
第●条 入退会
■記載マストその1.この会へは、自由意思で入会でき、また退会できる。
■記載マストその2.この会へ加入を希望する者は、加入届を提出する。
■記載マストその3.この会の退会は下記の通りとする
- 自動退会 子の卒業または転校等により、教職員会員については勤務校の異動により会員資格を失う者は、会員資格の消滅をもち退会とする。退会届提出の必要はない。
- 任意退会 自由意思によって退会を希望する者は、退会届を提出する。
※退会について触れるとともに、会費の返金についても記載が必要になります。
返金については下記の2パターンになると思います。
・「途中退会の場合、支払い済みの会費は退会後の翌月分からの月割で返金するものとする。」
・「途中退会の場合、支払い済みの会費は返金しない。」
「返金する」の場合、転出してしまった会員を事前にPTAで把握するのは難しく、返金先の口座を確認できないケースもありますので、下記のような書き方を推奨します。
「途中退会の場合、支払い済みの会費は退会後の翌月分からの月割で返金するものとする。ただし自動退会で返金の要請がない場合は返金しない。」
②規約チェックポイント、マストの4項目その2.
会費の徴収や督促などを学校に委ねている場合は、必ず委託契約書(準委任契約)が結ばれていることの記載が必要。
※本来PTA会費の徴収はPTAがやるべきですが、会員の引き落とし口座から引き落とす手続きをPTAが受け持つことへの負担感、要支援家庭などPTA会費が免除になる家庭をPTAが知ってしまう事への倫理的懸念、会費が支払われたかの突き合わせや督促の人的リソースの確保の難しさなどがあり、なかなかできないのが一般的です。
そこで学校に委ねるわけですが、PTAは学校とは別団体ですので、会員の個人情報を学校へ提供すること、会費の徴収に関わる業務を学校に委ねるには、法的にクリアする必要があります。
個人情報保護法の問題もそうですし、学校へ教材費の引き落としのために教えた口座から勝手にPTA会費が引き落とされることは「詐欺」だと思われかねません。
それをクリアするのが「委託契約書(準委任契約)」です。学校とPTAがこの契約を締結し、規約に記載しましょう。
(委託契約書(準委任契約)のひな形は-こちらから-ダウンロード可能です)
ちなみに、先生もPTAの「T」なので、P担当の先生が徴収や督促をするのは問題ないのでは?という質問も頂きますが、基本的に先生は教員の業務時間中に作業しますので、学校に委ねるということになります。
また、PTAに加入していない先生もいます。その先生がPTAの配布物を児童生徒に配布する作業をする、などPTAの業務をする場合もありますので、その意味でも委託契約書(準委任契約)は必要になります。
チェックする規約の個所はここ↓
【第●章 会員】
☑会費の徴収に関わる業務を学校にお願いしているのに、委託契約書(準委任契約)について書かれてない。(個人情報保護法違反の可能性)
記載例)
第●章 会員
第●条 会費
・(会費についての記載)
・(教員の会費についての記載)
・(途中入会、退会の会費についての記載)
・会費の集金及び督促、またそれに付随する事項に関しては、■■市立▲▲中学校PTAと■■市立▲▲中学校との間に締結した委任契約書に基づき、 ■■市立▲▲中学校に委任する。
③規約チェックポイント、マストの4項目その3.
個人情報保護規定について書かれていること。
※言わずもがなですが、2022年4月1日施行の改正個人情報保護法により、PTAも個人情報取扱業者となりました。個人情報取扱規則を設け、個人情報保護管理者を置き、会員から個人情報取り扱い承諾書をもらう必要があります。また、規約にも記載します。
(個人情報取扱規程のひな形は-こちらから-ダウンロード可能です)
チェックする規約の個所はここ↓
【第●章 会員情報の管理】
【第●章 役員の任務】
【第●章 役員及び会計監査委員の選挙】
☑そもそも「会員情報の管理」の項目がない。(個人情報保護法をしっかりと守っていると周知)
☑任務の中に個人情報保護管理者の記載がない。(個人情報保護法をしっかりと守っていると周知)
☑選挙に関わる個人情報の取扱いについて記載がない。(個人情報保護法をしっかりと守っていると周知)
記載例)
第●章 会員情報の管理
第●条 本会に関わる会員等の情報は、別途定める「■■市立▲▲小学校PTA個人情報保護規程」に従う。
記載例)
※ここでは会長が個人情報保護管理者を兼務するパターンを記載例にします。
第●章 役員の任務
第●条 会長の任務は次の通りとする。
- (総会や委員会の招集など)
- (運営委員会及び常任委員の委嘱など)
- (選挙管理委員の委嘱など)
- (臨時特別委員の正副委員長、委員の委嘱など)
- 「■■市立▲▲小学校PTA個人情報保護規程」に係る個人情報保護管理者を兼任する。
記載例)
第●章 役員及び会計監査委員の選挙
第●条 役員及び会計監査委員(教職員を除く)の選挙ならびに就任は、次のごとく行われる。
- 候補者指名委員会を次の通り設置する。
- 各学級より●名を選出する。
- 教職員より●名選出する。
- 指名委員長は、指名委員の互選により決める。
- 指名委員の任務は、次の通りとする。
- 指名委員長は、指名委員を決定後、直ちに全会員に発表する。
- 指名委員会は、書記と会計補以外の役員及び会計監査委員(教職員を除く)候補者の内諾を得て、選挙管理委員会に推薦する。
- 個人情報の取扱いは、「■■市立▲▲小学校PTA個人情報保護規程」 に従う。 三、 選挙管理委員の構成及び任務は、次の通りとする。
- 選挙管理委員は、会長が地域を考慮して委嘱した会員から構成する。
- 選挙管理委員会は、指名委員会が推薦した役員及び会計監査委員候補を会員に知らせる。
- 役員及び会計監査委員の候補者の追加は、前項の候補者発表後●日以内に会員の中から選挙管理員会に推薦することができる。 この場合、選挙管理委員会は直ちに全会員にこの追加を発表する。
- 新たに選ばれた役員、会計監査委員は4月に就任する。
- 指名委員・選挙管理委員は、その任務を終了したときに解任される。
※会計監査の透明性を保つように「教職員より●名選出する。」は記載マストになります。
※本来ですと選挙に係る公平性を保つために選挙管理委員が必要ですが、なり手不足から選挙管理委員を設置せずに、指名委員がその任務を負うケースもあります。その場合は規約の中の選挙管理委員を指名委員に置き換えてアレンジしましょう。
④規約チェックポイント、マストの4項目その4.
サポーター制を導入しているが規約に書かれていない。
※書かれていないからといって大きなトラブルになることはありませんが、総会で突っ込みどころになることはあり得ます。また、役員のなり手不足の為に、委員会の状況が毎年変わることはよくあります。規約で対応できるようにしておくと無理に役員を決めようとして強要や強制をしたりすることもなくなります。
さらに、万が一、サポーターがPTA活動中にケガをしたり事故を起こしたときに、サポーターの活動ががPTA活動であるという根拠として記載があったほうが良いと思います。
チェックする規約の個所はここ↓
【第●章 常置委員会および臨時委員会】
☑サポーター制に関する記載がない(状況に応じて対応できるようにしておく)
記載例)
第●条 常置委員会は各年度の会員数、時代のニーズなどにより、正副委員長や委員の引き受け手が集まらない場合、その都度ボランティアを呼びかける「サポーター制」での活動も可能とする。なお、●年以上委員が不在で、継続が不可能とした場合は総会を経て委員会を統合することも可能とする。
第●章 常置委員会および臨時委員会
~Chapter3 規約改正ToDo~
ここでは、規約改正にむけて行うステップを①~④に簡潔にまとめてみます。
①規約改正ToDoその1. 校長先生に相談→役員でよく話し合う
②規約改正ToDoその2. 改正するのは「規約」か「細則」か
③規約改正ToDoその3. 文章の作成と改正前と改正後の要点を作成
④規約改正ToDoその4. 規約=総会、細則=運営委員会で承認をとる
①規約改正ToDoその1. 校長先生に相談→役員でよく話し合う
まず、校長先生と充分な話合いが必要であることが、一番重要であることを理解しておきましょう。
なぜなら、、、ほとんどのPTAは規約に関しては素人集団です。
改正した内容が穴だらけであったり、理不尽であったり、期せずして学校側に迷惑をかけてしまうような内容になってしまうかもしれないのです。しかし、規約の内容は、代変わりしても延々と従い続ける必要が生じます。事前にきちんと校長先生に「意図」「改正内容」を伝え、ご理解をいただきましょう。
ご理解を頂いたら役員で内容についてよく話し合いましょう。
②規約改正ToDoその2. 改正するのは「規約」か「細則」か
もう一点、重要なのが改正すべきは「規約」なのか「細則」なのかです。
そもそも「規約」と「細則」の違いですが、
「規約」は基本的ルール
「細則」はより具体的なルール
です。
また、
「規約」は総会で決議が必要
「細則」は運営委員会の決議
で通ります。
こう聞くと、「じゃあ、細則にしよう」と思いがちですが、それが危険な場合もあります。
それは、細則では後々簡単に改定できてしまうからです。もし自己の立場の優位を考えたり、仲の悪い人を排除するなど、悪意を持って改悪を図ろうとされた場合、運営委員会の過半数であっさり議決してしまいます。
簡単には基本的ルールや譲れないルールは「規約」の方で改正しましょう。
記載例)
・規約
【第●章 常置委員会および臨時委員会】
・常置委員会の委員は保護者で構成する。
・常置委員会の定員については、細則に定める。
・細則
【第●条 常置委員会の定員】
委員の定数は次の通りとする。ただし選出委員数の増減は必要に応じて運営委員会で報告し承認を得るものとする。
- 広報委員 ●名を目安とする
- 学級委員 各クラスから●名、●名を目安とする
このように、委員会の定員が生徒数によってしばしば変わることが想定される場合などは細則の方で決める方法もあります。
そのほか、会費も変動が見込まれるようであれば
・規約
【第●章 会員】
第●条 この会の会員は会費を納めるものとする。(月額は細則で定める)
・細則
【第●章 会員】
第●条 この会の会員は会費を納めるものとする。
- 会費は一世帯につき月額●●●円とする。
- 教職員は月額●●●円とする。
これを参考に改正したい点が「規約」と「細則」どちらかなのか決めましょう。
③規約改正ToDoその3. 文章の作成と改正前と改正後の要点を作成
文章の作成と改正前と改正後の要点を作成します。 例として、第一章で書いた任意加入についてを改正したい場合をあげますと、
【改正前】
第●章 会員
第●条 入退会
- ●小学校に入学すると●●小学校PTA、▲▲市PTA協議会、■■県及び日本PTA全国協議会の会員となる
【改正後】
第●章 会員
第●条 入退会
・この会へは、自由意思で入会でき、また退会できる。
・この会へ加入を希望する者は、加入届を提出する。
・この会の退会は下記の通りとする
- 自動退会 子の卒業または転校等により、教職員会員については勤務校の異動により会員資格を失う者は、会員資格の消滅をもち退会と する。退会届提出の必要はない。
- 任意退会 自由意思によって退会を希望する者は、退会届を提出する。
このような感じです。校長先生、役員会で話し合って、「よし」となったら次のステップです。
④規約改正ToDoその4. 規約=総会、細則=運営委員会で承認をとる
ここからが最後の詰めです。まずは規約改正の方から見てみましょう。
◆ 総会の1週間以上前に全会員に改正案を配布します。
このときに
「なぜ改正が必要なのかを説明文で訴える」
「どこを変えるのか、改正前と改正後の要点を添付」
「規約改正案」
この3点が必要です。
◆1週間後、総会で可否を諮ります。
Googleフォームでの文書総会を例にしてましょう。
※対面式の総会の場合は、口頭と挙手で行います。
記載例)
- ●中学校PTAの皆さま
日頃より●●中学校のPTA活動にご協力をいただきましてありがとうございます。 - /●に配布いたしました規約改正案、改正点の要点のとおり、規約に記載の内容が現状の活動にそぐわないと判断いたしましたため、規約の一部を改正したいと思います。
(規約改正案、改正点の要点はこのフォームのお知らせのメールに再度添付してあります)
なお、PTA規約第●章 第●条「状況に応じて文書総会の形式を選択することもあり得る。」により文書総会とさせていただきたいと思います。何卒ご協力のほどお願いいたします。
第一号議案 規約改正
・賛成
・反対
のような感じになります。結果の集計が終わったら、その結果を再度全会員に報告します。
定足数、回答数、賛成票、反対票、結果の報告になります。
◆次に細則の場合です。
こちらはもっと簡単で、運営委員会で承認をとればOKです。結果が出たら、その結果を総会で全会員に報告します。こちらも定足数、回答数、賛成票、反対票、結果の報告になります。
令和7年4月7日